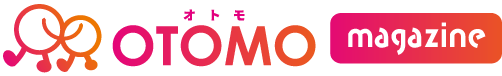※この記事には一部PRが含まれます。
「飲食店の就業規則について知りたい」
「個人経営でも就業規則は必要なのか知りたい」
法人化していない個人経営のお店で、従業員が守るべきルールや従業員の労働条件を定めた「就業規則」が必要なのか疑問に思う人もいるでしょう。
法人・個人事業主に関わらず事業を行い従業員を雇用していれば、就業規則は作成必須です。
本記事では飲食店で就業規則を定めるメリットから、作成時になにを記載すべきなのかその内容、具体的なテンプレートを紹介します。
飲食店の就業規則についてどのような項目を盛り込めば良いのかぜひ参考にしてください。
就業規則とは労働基準法により作成必須
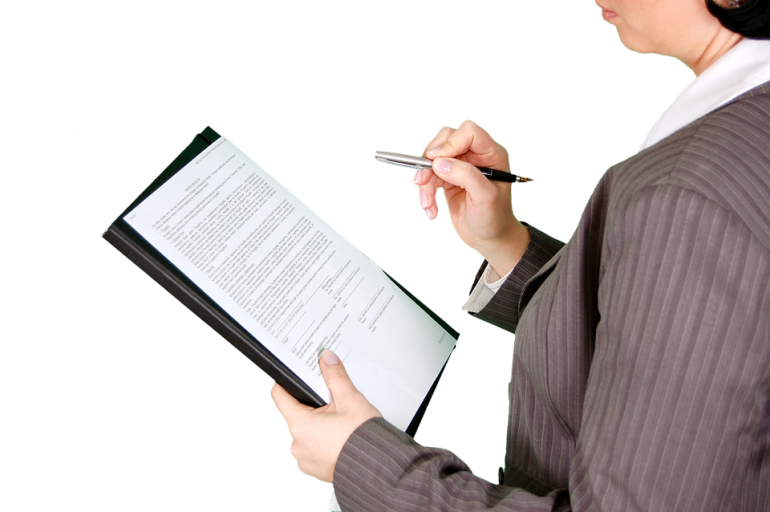
就業規則は、労働基準法第89条に基づき、作成しなければならないものと規定されています。
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
厳密には10人以上の従業員を雇っている場合の義務となりますが、1人でも従業員を雇っている場合、就業規則の作成をしておいた方が良いでしょう。
就業規則には、会社と従業員のそれぞれの権利や義務が文言として明記されるため、信頼関係の確立や規律の保持に役立ってくれるからです。
飲食店は、開店準備からお客様からのの注文、料理やドリンクの提供、お会計、後片付け、締め処理、閉店業務まで、1人では中々立ち回りが難しい仕事でしょう。
キッチンで調理している間にドリンクを運んだりオーダーを取る従業員は少なからず必須といえます。
従業員を雇う検討をする際には就業規則の作成も並行して行いましょう。
飲食店で就業規則を定める6つのメリット

飲食店で就業規則を定める6つのメリットを見ていきましょう。
- 社内の規範になる
- 人事労務管理が効率化する
- 会社の仕組みを明文化できる
- 人材を集めやすい
- 人件費の削減に繋がる
- 助成金申請に必要なケースがある
詳しく解説していきます。
社内の規範になる
就業規則は行動や判断をするための拠るべき規則や基準となる、社内規範になります。
経営者が毎日出勤しお店をまわしていても体調不良などの理由でその日の営業を従業員のみに店を任せる場面も出てくることでしょう。
そのような時でも規範となる就業規則があれば従業員は焦らずに対応することができます。
規範が無ければ従業員個人の考えに基づき行動を行い、判断ミスが起こる可能性もあるのです。
人事労務管理が効率化する
就業規則には社内ルールが規定されており、それに基づき業務を遂行することで、人事労務管理が効率化します。
- 人事管理:採用・育成・評価など、働く人材の管理を行う業務
- 労務管理:勤怠管理や給与計算、福利厚生手続きなど、職場環境を整える業務
例えば人事管理で人材の評価を行う場合、社内ルールが無ければ、どのような基準で評価をして良いのか迷ってしまいますよね。
従業員側も満足度の低下につながる恐れもあります。
定期的にスムーズに人事労務管理を行うためにも、就業規則を設定すると良いでしょう。
会社の仕組みを明確にできる
まだ従業員も数名の小さな店舗で、従業員との意思疎通も問題なく行われているかもしれません。
今後事業拡大していく予定の飲食店であれば、会社の仕組みを明確にしておくことが重要です。
会社が発展し現場に出ていた経営者はマネジメント側に回ることで、社員1人1人とのコミュニケーションが自然と少なくなる可能性があります。
経営者の考え方を直接言葉にして伝えられなくても、経営者の想いをした就業規則があれば、社員皆に知ってもらうことができるのです。
社員に会社の仕組みを知ってもらうことで、育成や教育なども効率的に進むでしょう。
人材を集めやすい
飲食店は残業が必要であったり早上がりになる可能性があるなど流動的な職場ではありますが、基本的な労働時間は何時間、有給日数は何日など、就業規定に記載しておくと人材が集まりやすい傾向があります。
人材の応募があっても定着しないと悩んでいる経営者は特に、就業規則を作って労働条件を整備してみましょう。
雇用される立場から見て、どのような就業規則が規定されていると安心かを考えて、内容を盛り込むと良いかもしれません。
人件費の削減に繋がる
就業規則を設定することで、うまくいけば人件費の削減ができる可能性があります。
飲食店は忘年会や新年会の開催が増える年末年始や、大型連休のゴールデンウィークなどは忙しく、2月、8月は比較的閑散期というケースが多いようです。
そこで就業規則に「変形労働時間制」を盛り込んでおくと、一定の期間における法定労働時間の総枠の範囲内で、1日または1週間の法定労働時間を超えて労働させることができるようになります。
- 毎日7時間労働を辞め、12月〜1月と5月の繁忙期は9時間労働、残りの9ヶ月は6時間労働とする
変形労働時間制をうまく活用することによって、時間内であれば残業代を支払う必要がないため、人件費の削減が期待できます。
助成金申請に必要なケースがある
国や地方団体から支給される助成金を申請するためには、就業規則の提出が支給要件になっているものもあります。
労働法では従業員が10名以上いる場合に就業規則の作成と届け出は義務となっていますが、助成金申請をする際に就業規則の提出が義務となっている場合は、規模に関わらず必要です。
助成金の提出段階になって初めて間に合わせで作成するのではなく、せっかくであれば従業員や事業のことをきちんと考えた上で前もって作成した就業規則を提出するようにしましょう。
飲食店の就業規則作成で必要な2つの事項

飲食店の就業規則を作成するには、2つの事項を盛り込む必要があります。
- 絶対的必要記載事項
- 相対的必要記載事項
それぞれの事項について詳しく見ていきましょう。
絶対的必要記載事項
絶対的必要記載事項とは法律上、就業規則に必ず記載しなければいけない事項です。
- 始業時刻
- 終業時刻
- 休憩時間
- 休日
- 休暇
- 交替制の場合は就業時転換に関する事項
- 賃金の決定
- 計算及び支払いの方法
- 賃金の締切
- 支払いの時期
- 昇給に関する事項
- 退職に関する事項
就業規則の中に上記が抜けている場合には、法律に基づき不備となるため必ず規定しておきましょう。
相対的必要記載事項
相対的必要記載事項とは、制度がある場合に必ず就業規則に記載しなければならない事項です。
- 退職手当
- 臨時の賃金(賞与)
- 最低賃金額
- 食費、作業用品などの負担
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補助、業務外の傷病扶助
- 表彰、制裁
- その他全労働者に適用される事項
制度を設けていなければ、就業規則に記載する必要はありません。
就業規則を作成する際には、それぞれの内容を確認し、どのような規定を設けるかあらかじめ決めておきましょう。
飲食店で就業規則を作成する際の5つの注意点

飲食店で就業規則を作成する場合の注意点を5つお伝えします。
- 法律に違反しない内容となっている
- 労働条件の最低基準を定められている
- 従業員の意見を反映できている
- アルバイト・パートへの退職金の有無を決める
- 雇用形態によって分ける
以下で詳しく説明します。
法律に違反しない内容となっている
就業規則とは、労働基準法に基づき制定するものですので、法律に違反している部分に関しては無効となります。
- 労働・残業時間が週40時間、または36協定で合意した範囲を超えている
- 6時間を超える労働の場合は45分、8時間を超える労働の場合は60分以上の休憩が必要だが、これがない
- 週1日以上の法定休日がない
- 残業・休日出勤・深夜の労働をしたのに手当がない
労働基準法違反の内容は従業員に周知していなくても無効であり、労働基準監督署から指導勧告や命令を受ける可能性もあります。
就業規則を作成する際には、労働基準法をしっかりと確認の上、行いましょう。
労働条件の最低基準を定められている
昭和22年に定められた労働基準法では、労働条件における最低基準を以下のように定めています。
| 賃金支払 | 直接払、通貨払、全額払、毎月払、一定期日払 |
| 労働時間 | 週40時間、1日8時間 |
| 時間外・休日労働 | 労使協定の締結 |
| 割増賃金 | 時間外・深夜2割5分以上、休日3割5分以上 |
| 解雇予告 | 30日以上前の予告または30日分以上の平均賃金の支払 |
| 有期労働契約 | 原則3年、専門的労働者は5年 |
就業規則に労働基準法違反の内容を載せた場合、労働者は違反の事実を行政官庁または労働基準監督官に申告することができますが、事業主はその申告を理由として労働者に対し、解雇その他不利益な扱いをすることはできません。
違法な内容が無いかは、再三のチェックの上、十分に注意しましょう。
従業員の意見を反映できている
就業規則は会社と従業員のため、従業員の意見を反映することが大切です。
意見を聞く従業員は、経営者サイドに立つ管理監督者ではなく、一般の従業員がふさわしいです。
従業員の意見を反映できない環境では、信頼関係の低下にも直結するため注意しましょう。
就業規則を作成または変更し届け出する際には、労働者の代表から意見をまとめた「意見書」の添付が義務づけられています。
労働者側の意見を十分に聞いた上で、就業規則を作るようにしてください。
アルバイト・パートへの退職金の有無を決める
アルバイト・パートへ退職金を支払うかどうかを決められます。
2021年4月、パートタイム・有期雇用労働法が施行されました。
正社員とパートタイム労働者、有期雇用労働者との不合理な待遇差を禁止するなど、パート・アルバイト・契約社員として働く方の環境を良くするための法律です。
※「パート」、「アルバイト」といった呼称の違いによらず、「パートタイム・有期雇用労働法」の対象になるのは以下の方です。
○正社員(通常の労働者)と比較して1週間の所定労働時間が短い労働者
○有期雇用(1年や3年など定めがある労働契約)で働く労働者
引用;パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のために
正社員やアルバイトなど分け隔てなく不合理な待遇差を禁止する法律が施工されたため、アルバイトは退職金を受け取れる権利を有しています。
就業規則や契約内容によってもらえる要件等定められるため、就業規則で決める必要があります。
雇用形態によって分ける
雇用形態によって就業規則を分けることも重要です。正社員やアルバイトなど正規雇用と非正規雇用によって、就業規則の内容も変わってきます。
そのためそれぞれの項目に分けて、作成する必要があります。
雇用形態によって冊子を別にしておくと、齟齬なく進められるため実践してみましょう。
【雛形あり】飲食店の就業規則の無料のテンプレート・サンプル3選

就業規則を作成するメリットや注意点を理解した上で、いざ作成しようと思っても何から手をつけて良いか、分からない人も多いですよね。
最後に飲食店の就業規則作成時のテンプレートを3つ紹介します。
- 厚生労働省
- rumu.com
- ビスオーシャン
内容を参考に、自身の飲食店に沿った就業規則を作り上げてくださいね。
厚生労働省
- 参照:厚生労働省「モデル就業規則」
厚生労働省が作成している、モデル就業規則です。
Word形式やPDF形式、英語・中国語・ポルトガル語・ベトナム語の外国語版も見られます。
規程例や解説を参考に、各事業所に応じた就業規則を作成し、届け出するようにしましょう。
rumu.com
- 参照:rumu.com「就業規則テンプレート集」
正社員・パートタイマー・嘱託など、雇用形態の分かれた就業規則のテンプレートが見られます。
Word形式、PDF形式、テキスト形式でダウンロード可能です。
ビスオーシャン
- 参照:ビスオーシャン「就業規則の書式テンプレート」
就業規則の他にも、就業規則作成のチェックポイントや、社員に対して就業規則への違反を理由に解雇することを通知する書類、リフレッシュ休暇制度を規定するための雛形など、様々な書式のダウンロードができます。
まとめ
10人以上の従業員がいる事業所に提出義務がある就業規則ですが、経営者と従業員の信頼関係を守るためにも、1人以上の従業員がいれば、作成しておいた方が良いでしょう。
就業規則は労働基準法に基づき制定されているため、法律違反をしてしまうと、労働基準監督署から勧告や命令を受ける可能性があります。
現在経営している飲食店を従業員とともに盛り上げて大きくしていくために、従業員の意見も取り入れながら、正しい就業規則を作成していきましょう。
\ 【無料相談】LINEでの相談も受付中! /