※この記事には一部PRが含まれます。
近年、実店舗を持たずにデリバリーだけで営業する「ゴーストレストラン」が注目を集めています。
初期費用を抑えながら新しいブランドを立ち上げられる一方で、意外と多くの人が悩むのが“仕入れ”の部分。
ゴーストレストラン運営において、「仕入れ」は利益を左右する最も重要な要素です。
限られたスペースで、どうやって必要な食材をムダなく、安定して仕入れるか——。
本記事では、「小ロット・高回転」で利益を最大化するためのゴーストレストランの仕入れ戦略を徹底解説します。
仕入れの最適化は、そのまま経営の安定化に直結します。これからゴーストレストランを始める方、あるいは今の仕入れに課題を感じている方は、ぜひ最後までご覧ください!
ゴーストレストランでも「仕入れ」が重要な理由

「ゴーストレストラン」は、実店舗を持たずにデリバリーだけで営業でき、低コストで開業できる魅力があります。しかし“仕入れ”の考え方を軽視すると、すぐに利益が圧迫されるのもこの業態の特徴。
この章では、なぜゴーストレストランにおいて仕入れの工夫が欠かせないのか、実店舗との違いを交えて解説します。
仕入れの工夫が利益を左右する
ゴーストレストランの収益構造を考える上で、まず無視できないのがデリバリープラットフォームの手数料です。売上の30%から40%にもなるこの手数料が、粗利益を大きく圧迫します。そのため、手数料を支払った後に最終的な利益を確保するためには、食材の仕入れコスト(原価)をいかに徹底的にコントロールするかが不可欠となります。原価率をわずか1%でも下げることは、最終利益率に大きな影響を与えます。販売価格を自由に上げにくいデリバリー業界において、仕入れの現場こそが利益を生み出すための「コストカットの最前線」となるのです。
実店舗と違い「スペース」「保存期間」に制約がある
店舗を持たない分、冷蔵・冷凍スペースが限られているケースが多く、仕入れ量を読み違えると在庫がすぐにパンクします。この制約のため、従来の飲食店経営でよく用いられる「大量仕入れによるコストダウン(スケールメリット)」を追求することが困難です。
また、調理スタッフが少ないため、仕込み時間を短縮できる“保存性の高い食材”を選ぶ工夫も必要となります。
小ロット・高回転が経営の鍵になる
上記の制約を踏まえ、ゴーストレストランで追求すべき仕入れ戦略は「小ロット・高回転」の実現です。一度に仕入れる量は極力少なく抑え(小ロット)、在庫リスクとフードロスを最小限に留めます。そして、仕入れた食材を短期間で使い切って売上に変えること(高回転)で、食材の鮮度を保ちつつキャッシュフローを安定させます。この「小ロット・高回転」を実現するためには、頻繁な仕入れ、需要予測に基づいた仕入れ量の緻密な調整、そして汎用性の高い食材の選定が、ゴーストレストランの仕入れにおける基本原則となります。
この考え方が、後のデリバリー需要変動にも柔軟に対応できる強みになります。
ゴーストレストランの仕入れ方法3パターン

ゴーストレストランの運営規模やメニューの専門性によって、最適な仕入れ先は異なります。
スペースや人員が限られている分、効率と柔軟性を重視した仕入れルート選びがポイントです。
ここでは、低コスト運営を成功させるために知っておくべき、主要な仕入れ方法を3つご紹介します。
この仕入れ方法は、ゴーストレストランの立ち上げ初期や、特定日・時間帯の急な食材補充に非常に有効です。
一般的なスーパーや業務用スーパーは、誰もがアクセスしやすく、必要な分だけ(小ロットで)すぐに仕入れられる手軽さが最大のメリットです。また、少量であれば、卸業者と比べて価格差が小さい場合もあります。
しかし、大量の注文には対応できず、仕入れ価格が安定しないため、事業が軌道に乗って注文が増えてきた際には、仕入れコストがかさむ原因となり得ます。あくまでも「緊急時」または「小規模運営時のつなぎ」として利用するのが賢明です。
「試作段階」や「副業での小規模運営」には向いていますが、継続的な販売を視野に入れるなら、もう一歩踏み込んだ仕入れルートを検討したいところです。
ゴーストレストランで安定した収益を目指すなら、オンラインで完結する仕入れサイトの活用が圧倒的におすすめです。実店舗を持たないゴーストレストランにとって、仕入れサイトの活用は「時間と手間」を大幅に削減できるため、調理や集客といった他の重要な業務に集中できるようになります。
特に仕入れサイトの強みは、
- 食材/調味料/資材などをまとめて発注できる
- 過去の発注履歴からリピート発注が簡単
- 定期配送/在庫管理まで一括で管理できる
- 卸売価格で食材を調達できるため、スーパー仕入れに比べて原価率を改善しやすい傾向にある
- 配送頻度や時間指定の柔軟性が高い
といった効率面にあり、「小ロット・高回転」戦略を最も実行しやすくなります。
小規模かつ効率的なゴーストレストランの運営基盤を作る上で、仕入れサイトの活用は欠かせません。
初期費用を抑えながら品質を安定させたい人にとって心強い味方です。
最近では、少量注文・翌日配送・キャッシュレス決済など、
ゴーストレストランの運営スタイルにピッタリのサービスが増えています。
仕入れサイトの詳しい解説は下の記事をご覧ください!
 飲食店の仕入れはどうする?業態別に選ぶべき仕入れサイト9選【開業初期〜小規模店向け】
飲食店の仕入れはどうする?業態別に選ぶべき仕入れサイト9選【開業初期〜小規模店向け】
この仕入れ方法は、顧客への提供価値を高め、メニューやブランドの差別化を図りたい場合に有効です。特定の地域の農家や漁師など、生産者と直接契約を結ぶことで、スーパーや卸では手に入らない独自の高品質な食材を確保できます。
生産者の顔が見える食材は、ストーリー性があり、メニューの説明や集客時のアピールポイントとして強力な武器になります。また、地元野菜やブランド肉など、素材を前面に出すメニューを展開することで、デリバリーアプリ上でも「選ばれる理由」を作り出すことができます。しかし、デメリットとして、仕入れ値が比較的高くなること、そして供給量が天候などに左右され不安定になりやすいことが挙げられます。そのため、看板メニューなど特定の高付加価値メニューに限定して導入するなど、戦略的に活用することが求められます。

ゴーストレストランは、スピードと柔軟性が命!
「仕入れサイトを軸に、小売や直送で補う」ハイブリッド型が、
コスト・手間・品質のバランスを取りやすい仕入れ戦略です。
仕入れで失敗しないための3つのコツ

仕入れのバランスを誤ると、どんなに美味しいメニューを作っても利益が残りません。限られたスペースと高いプラットフォーム手数料という制約の中で、ゴーストレストランが安定して利益を出すためには、仕入れの段階でリスクを最小限に抑える工夫が必要です。ここでは、食材のロスを防ぎ、原価率を適正に保つための具体的な3つのコツを解説します。
① 仕入れ頻度を“需要サイクル”に合わせる
仕入れで失敗する大きな原因の一つが、需要予測と仕入れ量のズレによって発生する食材の廃棄、すなわちフードロスです。これを防ぐためには、仕入れの量を調整するだけでなく、仕入れの頻度自体を需要のサイクルに合わせることが重要になります。たとえば、週末に注文が集中し、平日は緩やかになるサイクルであれば、週末前の仕入れを多めに、週明けの仕入れを絞るように調整します。理想は、在庫スペースが許す限り、仕入れ量をギリギリまで絞り、頻度を上げることです。これにより、食材の鮮度を保ち、在庫の長期滞留を防ぎ、「小ロット・高回転」の戦略を確実に実行できます。
仕入れサイトを使えば、需要の波に合わせて発注量を柔軟に調整できます。
在庫管理データや販売履歴をもとにした「発注リズム」を掴むことで “仕入れすぎ” も “仕入れ不足” も防げます。
② 同じ食材で複数メニューを構成してロスを防ぐ
食品ロスを根本から防ぐための最も有効な戦略の一つが、メニューの絞り込みと食材の汎用性の最大化です。ゴーストレストランでは、メニューを絞ることが重要ですが、仕入れた食材を“1つの用途だけ”で終わらせるのはもったいない。例えば、鶏もも肉を「唐揚げ丼」と「チキンカレー」の両方のメイン食材として使用できるようにメニューを構成します。この「クロスユース」戦略によって、仮に「唐揚げ丼」の注文が減っても、その食材を「チキンカレー」で消化できるため、食材が廃棄になるリスクを大幅に下げることができます。ゴーストレストランは専門性が高いためメニューを絞りがちですが、使用食材は絞り、その食材から複数のメニューを展開するという工夫が、仕入れの安定化とロス削減に直結します。
仕入れサイトを使うと、同系統の食材をまとめて探せるため、メニュー構成を考える段階でロス削減を設計できるのも利点。
“調達と開発をセットで考える”ことが、効率的な運営につながります。
 飲食店の仕入れはどうする?業態別に選ぶべき仕入れサイト9選【開業初期〜小規模店向け】
飲食店の仕入れはどうする?業態別に選ぶべき仕入れサイト9選【開業初期〜小規模店向け】
③ 保存・配送コストまで含めて原価率を考える
仕入れの価格(購入価格)だけを見て「安い・高い」を判断すると、思わぬ落とし穴があります。ゴーストレストランでは、仕入れの「隠れコスト」にも目を向ける必要があります。具体的には、配送コスト(送料)と、食材を保管するための保存コスト(電気代など)です。特に小ロットで頻繁にネット仕入れを利用する場合、都度発生する送料が無視できないコストになることがあります。また、特定の食材を保存するために特殊な冷蔵・冷凍設備が必要な場合、そのランニングコストも考慮に入れるべきです。
仕入れサイトなら、温度帯別の配送や送料体系も明確で、1配送あたりの総コストを把握しやすいのが強み。
長期的に見ると“手間を減らしながら安定した品質を維持する”ことが、もっとも大きなコスト削減になります。
💬失敗を防ぐ仕入れの三原則
- 需要に合わせて仕入れ量を変える
- 同食材を使いまわしてロスを減らす
- 原価は「仕入れ+保存+配送」で考える
この3つを押さえれば、どんな規模のゴーストレストランでも“黒字体質”に近づきます。
ゴーストレストランならではの仕入れ戦略

初期費用や固定費を抑えることができたとしても、ゴーストレストランの競争は激化しています。生き残り、利益を最大化するためには、実店舗には真似できないデリバリー専門業態ならではの柔軟性とデータを活用した仕入れ戦略が不可欠です。ここでは、ゴーストレストランを次のレベルに引き上げるための具体的な戦略をご紹介します。
ゴーストレストランの運営において、最も強力な武器となるのがデリバリープラットフォームが提供する需要データです。実店舗では感覚に頼りがちだった需要予測を、アプリの売上データや地域ごとの注文トレンド、曜日・時間帯別の人気メニューといった具体的な情報に基づいて行えます。たとえば、アプリの管理画面から得られる「注文が多い時間帯」に合わせて仕入れの検品や下準備のタイミングを調整したり、「競合店で今売れているジャンル」を参考に、仕入れやすい汎用食材で新メニューを開発したりといった戦略的な判断が可能です。
データに基づいた仕入れ調整こそが、過剰在庫のリスクを回避し、最も効率的に「高回転」を実現する鍵となります。
ゴーストレストランでは、仕込みスペースや冷蔵設備が限られています。
だからこそ、保存期間と調理効率のバランスを考えた食材選びが大切です。
例えば、パンや冷凍肉といった日持ちする冷凍商材をストックすることで、急な大量注文や悪天候による配送遅延にも対応できる安定供給の基盤を作ります。一方、野菜や鮮魚など、料理のクオリティを左右するフレッシュな食材は、鮮度を保てる最小ロットで頻繁に仕入れる「高回転」を徹底します。このように、すべての食材を「生」で仕入れるのではなく、メニューごとに最適な保存形態(冷凍・冷蔵・常温)を選定し、仕入れ先を使い分けることが、在庫管理の負担を減らし、安定した品質を保つ上で非常に重要になります。
仕入れサイトを活用すれば、「冷凍」「常温」「チルド」といった温度帯ごとにカテゴリが分かれているため、仕込みの流れに合わせた発注計画を立てやすくなります。メニュー設計の段階から保存方法を意識するだけで、ロス削減と作業効率アップを同時に実現できます。
シェアキッチン(クラウドキッチン)を利用している場合や、同じビル・エリアにゴーストレストランを運営する事業者がいる場合、「共同仕入れ」という強力な戦略が利用できます。共同で大量に発注することで、本来ゴーストレストラン単体では難しかった卸業者からの大ロット割引や送料無料の恩恵を受けることが可能になります。また、シェアキッチン運営者が用意している共通の仕入れルートを活用すれば、個別の仕入れ手続きの手間を省くこともできます。周囲の事業者と連携を取り、特定の汎用食材(油、米、調味料など)をまとめて仕入れることで、単独では実現が難しかったコストダウンを実現し、利益率を大きく改善することができるのです。
💬ゴーストレストランの仕入れは、効率×柔軟性×協働がカギ
デリバリー需要を読み取り、保存効率を高め、仕入れをシェアする。
この3つを回せば、限られた環境で無理なく利益を出せる運営が実現します。
成功しているゴーストレストランの共通点

成功しているゴーストレストランには、共通する“仕入れの考え方”があります。
それは「手間をかけないこと」でも「安さを追うこと」でもなく“ムダのない仕組みで安定的に利益を出す”という姿勢。ここでは、安定した経営を続けるために必要な、成功店の共通点を解説します。
メニューを絞って仕入れを最適化している
成功しているゴーストレストランほど、扱うメニューが驚くほど少ないものです。メニュー点数が少ないほど、使用する食材の種類が限定され、その限られた食材に特化して仕入れを行うことができます。これにより、在庫ロスが減るだけでなく、同じ食材を複数メニューに使い回せるため、原価率をコントロールしやすくなります。少品目・高回転型の仕入れは、ゴーストレストランの理想的なスタイルといえるでしょう。
仕入れ先を固定せず柔軟に対応している
安定した価格と供給量を確保するために、成功店は仕入れ先を一つに固定せず、柔軟に対応する戦略を取っています。仕入れサイトを中心に、業務スーパーや地域の卸をサブルートとして活用すれば、価格変動や在庫不足のリスクを回避できます。このようなリスク分散の姿勢が、特定の仕入れ先での価格高騰や供給停止といった予期せぬトラブルから経営を守ります。複数の仕入れ先を比較できる環境を作ることで、常に最適コストで安定した供給を確保できるようになります。
原価・利益・在庫の“可視化”を徹底している
成功しているゴーストレストランは、感覚で動かず数字で判断しています。在庫管理や原価計算にデジタルツールを積極的に活用し、経営の「可視化」を徹底しています。
どの商品がどれだけ売れ、どの仕入れが利益を圧迫しているのか——。
彼らは、POSシステムや仕入れ管理システムを連携させ、食材の在庫状況、原価率、そしてメニューごとの利益をリアルタイムで把握できる体制を構築しています。この正確なデータに基づき、「売れ行きが鈍化しているメニューの食材を別のメニューに転用する」「需要予測に基づいて仕入れ量を細かく調整する」など、迅速で客観的な経営判断を下しています。感覚ではなく、データに基づいた緻密な管理こそが、彼らが安定して高い利益率を維持できている最大の共通点です。
💬成功している店は「仕入れをシンプルに、判断をデータで」
ゴーストレストランの勝ちパターンは、少品目×柔軟ルート×可視化経営の3つ。
感覚に頼らず、データと仕組みで動かすことが、長期的な成功を支えています。
まとめ|仕入れを整えれば、ゴーストレストランはもっと続く

ここまで、ゴーストレストランの低コスト運営を実現するための仕入れ戦略を、多角的に解説してきました。
ゴーストレストランは低コストで始められる反面、仕入れ・在庫・原価のバランスを誤ると、すぐに赤字に転じてしまう業態です。
しかし逆に言えば、仕入れの仕組みさえ整えば、長く安定して続けられるビジネスでもあります。
最後に、本記事で得た知識をどのように経営へ活かすべきか、重要なポイントを改めて確認していきましょう。
ゴーストレストランの経営では、デリバリープラットフォームの高い手数料と、限られたスペースでの在庫管理が大きな課題です。
これらを克服し、安定して利益を出すためには、仕入れの最適化が欠かせません。
仕入れは単なる“食材の調達”ではなく、経営の土台そのものです。
仕入れ頻度・仕入れ先・食材構成を見直し、発注から販売までのサイクルを整えることで、原価率・作業効率・リピート率のすべてを安定させることができます。
特に仕入れサイトを活用すれば、発注履歴やコストの推移をデータで管理でき、「今月どれくらい仕入れに使っているか」を即座に把握できます。
感覚ではなく数字で仕入れを管理することが、売上変動の激しいデリバリー業界で経営を安定させる最短ルートです。
 飲食店の仕入れはどうする?業態別に選ぶべき仕入れサイト9選【開業初期〜小規模店向け】
飲食店の仕入れはどうする?業態別に選ぶべき仕入れサイト9選【開業初期〜小規模店向け】
ゴーストレストランは、実店舗に比べて格段に低リスクで始められるビジネスですが、“最初から完璧”を目指す必要はありません。
まずは「スーパー・業務スーパー仕入れ」など手軽な方法から小さくスタートし、販売量やリピート数を見ながら、仕入れサイトや卸との契約へ段階的に移行していく流れが理想です。
重要なのは、「小ロット・高回転」という基本原則を常に意識し、在庫を抱えすぎずに食材を賢く回していくこと。
こうした着実な運用こそが、長く続く成功への第一歩となります。
仕入れの仕組みが整ったら、次は「売上アップの仕掛け」を意識しましょう。
以下のようなデリバリーサービスを活用すれば、販売チャネルを一気に拡大できます。
- Uber Eats(ウーバーイーツ)
- Rocket Now(ロケットナウ)
- menu(メニュー)
- Wolt(ウォルト)
複数サービスを併用することで、時間帯・地域・客層の幅が広がり、自然と売上の安定につながります。
さらに、アプリ上の売上データを仕入れの調整に活かせば、“仕入れと販売が連動する”理想の経営サイクルを築けます。
👇関連記事はこちら👇
 【2025年最新】デリバリーサービスを導入する方法とは?飲食店におすすめのサービス5選!
【2025年最新】デリバリーサービスを導入する方法とは?飲食店におすすめのサービス5選!
 失敗しないデリバリーアプリ選び:UI・導線・追跡・決済・再注文を徹底評価!
失敗しないデリバリーアプリ選び:UI・導線・追跡・決済・再注文を徹底評価!
\今すぐ無料でお見積もり!/
いくら仕入れコストを下げても、メニューの質が落ちて顧客満足度が下がれば、リピート率が低下してしまいます。逆に、最高級の食材を仕入れても、高すぎて売れなければ利益は出ません。
大切なのは、仕入れと販売の両輪をバランスよく回すことです。
仕入れサイトで原価を抑え、
デリバリーアプリで売上を広げ、
そのデータをもとに次の仕入れを決める——。
この循環ができれば、ゴーストレストランは“自動で回る経営モデル”として安定的に成長していきます。
 飲食店の仕入れはどうする?業態別に選ぶべき仕入れサイト9選【開業初期〜小規模店向け】
飲食店の仕入れはどうする?業態別に選ぶべき仕入れサイト9選【開業初期〜小規模店向け】
最後に———
OTOMOでは、こうした飲食店経営の「仕組み化」を支援する情報を発信しています。
今日からできる小さな工夫で、あなたのゴーストレストランを
“もっと強く、もっと長く”.
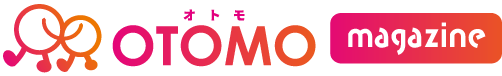
\ 【無料相談】LINEでの相談も受付中! /

